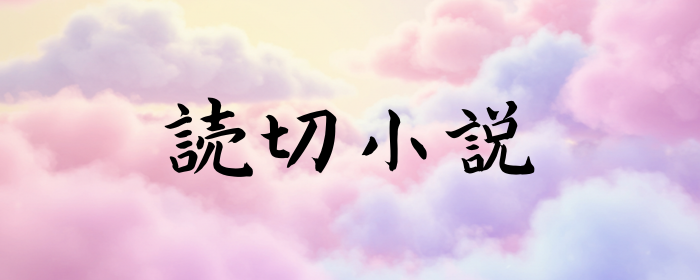
あらすじ
都内で廃墟探索系YouTuberとして活動する31歳の女性・美咲は、過去の事故で片耳の聴力を失い、彼女の作品は「無音」の映像と字幕で構成されている。奥多摩の廃村跡での撮影中、かつてそこで暮らしていた男性・隆志と出会い、対立から始まった関係は、記憶と記録の境界をめぐる対話へと変わっていく。
無音の映像は、ときに人の体温を消してしまうのではないか——そんな問いに向き合いながら、美咲は「残すこと」と「残さないこと」の狭間で選択を迫られる。やがて彼女は一本の動画を非公開にし、別の撮り方を選ぶ。記録は消えても、記憶は生き続ける。その静かな到達点までの物語。
十一月の冷たい山風が頬を刺す。奥多摩線の終点からさらにバスと徒歩で山を分け入ると、蔦に覆われた木造家屋や崩れた梁が、時の止まった風景として現れる。美咲は三脚を立て、ミラーレスの設定を確かめた。無音の動画は細部の揺らぎが命だ。画面の隅で枯葉が石段に落ちる。
「ここ、撮影はやめてもらえますか」
振り返ると、作業着の中年男性が立っていた。日焼けした肌に刻まれた皺、古い傷の残る手。男は隆志と名乗り、ここを「荒らされたくない場所」だと言った。
「近隣の方ですか」
「近隣ってほどの近隣は、もうないけど。観光感覚で来る人が増えて、家の中の物が持ち出されたりするんです」
「撮るだけです。触れません」
「俺、隆志。ここで少し暮らしてたことがある」
隆志は、廃村に身を寄せていた日々を語った。倒産、離婚、住まいの喪失。雨漏りする屋根をビニールで覆い、川辺の石でかまどを組み、夜は焚き火の橙に頼ったという。美咲が切り取る「美しい廃墟」は、誰かの生活の跡そのものだった。
「暮らしていた?」
「最初は雨風がしのげればよかった。でも、そのうち守りたくなった。ここに残った誰かの鍋や器具、勝手に捨てられなかった」
「あなたの動画、見ました。きれいすぎる。ゴミも落書きも、画面から消えている」
「構図と光と距離で外してます。映したくないものは入れない」
「そうやって『生活』も消える」
焚き火の脇で、二人は黙って炎を見つめた。パチ、と乾いた音が橙の中に消える。美咲は、無音の画面に置く字幕の冷たさを思い出していた。鑑賞物としての静けさは、ときに人を透明にする。
「最初は生き延びるため。でも、だんだん分かった。記憶は個人のものじゃない。混ざり合って、誰かの中に生きる」
「顔は映しません。約束します」
美咲はカメラを下ろし、話を聴くためだけに通う日をつくった。残された食器、柱の身長記録、畳に転がるビー玉。どれもが「ここに人がいた」証だった。
数週間、撮影しない日も通った。歩き、確かめ、聴く。無音のままでも、人の体温を消さない撮り方を探す。
「動画にしないんですか」
「いつか。急ぎたくない」
美咲は事故の日を思い出す。世界の半分だけが音を持ち、もう半分は沈黙のまま取り残された感覚。彼女の「無音」は、表現であり現実だった。
ある夜、炎の陰影が隆志の頬に小さな影を作った。
「ここを出たのは、怖くなったから。誰にも会わないでいると、自分が透明になっていく」
「今は?」
「清掃の仕事。朝が早いけど、汚れが落ちるのは気持ちいい」
その瞬間を、美咲は撮らなかった。無音の画面に残すより、胸の中に留める方が正しいと思った。
やがて一本の動画が完成した。サムネイルは蔦に覆われた窓。字幕は最小限に、隆志の言葉を運ぶ。
「ここにあった生活を、ただ『きれい』と言い切るのが怖い」
公開直後から反響が広がる。共感と賛否が同居し、「感傷商法」「貧困ポルノ」という冷たい語が画面を流れた。隆志は沈黙し、美咲も沈黙した。
数日後、美咲は動画を非公開にした。代わりに短いテキストを投稿する。「これは、誰かの生活の跡であり、誰かのこれからでもある」。
冬の入口、二人は石段で別れを交わした。
「ありがとう」
「何もしてない」
「見てくれたから」
春、無音の映像は変わった。空き家の壁に残るメモ、棚の空き瓶、床に落ちた写真。かつてなら切り落としていた断片を、いまは画面の中心に置く。フォロワーは減ったが、彼女は続けた。
港町の倉庫跡で、木枠に挟まった古い手紙を見つける。封は切らず、ただ光の中に置く。公開後、「祖父が働いていた場所かもしれない」というコメントが寄せられ、断片がつながっていく。無音が、誰かの記憶を呼び起こしていた。
秋の終わり、廃村に戻る。倒木の跡、崩れた土壁。季節とともに形は変わる。石段の途中で、一枚のメモが風に貼りついていた。読み取れるのは五文字だけ——「ありがとう」。
持ち帰らない。置いていく。ここにあったものは、ここに残す。
都心の夜。編集を終えた映像を見返す。字幕は少なく、呼吸の間を残す。画面の向こうに「見ている誰か」がいると思うと、胸の真ん中に小さな火が灯った。
メールが届く。差出人は隆志だった。
『美咲さん。介護の仕事を始めて一年。毎日が学びです。記憶は現在進行形だと感じます。過去は人の中で生まれ直す。あなたの映像も、誰かの記憶の一部になるでしょう』
美咲は静かに返信を打つ。
『お元気そうで何よりです。私も学び続けます。無音でも人の体温を消さないように。記録する責任を忘れません』
窓の外の夜景の奥に、あの廃村の静けさが重なる。記録は消えても、記憶は残る。無音の画面の奥で、確かに聴こえるものがある——人の気配、時間の重さ、まだ言葉にならないやさしさ。